第二種電気工事士技能試験の問題は
単線図で出題されますが、
作る前に単線図を複線図に
書き直さなければなりません。
筆記試験でも複線図を書いた方が
解りやすい問題が何問か出ますので、
筆記試験勉強の時についでに公表問題を
複線図に書き直す練習をしておけばよいかと思います。
特に難しくなく、書く順番が決まっており、
最初は考えながらでも、何度か書けば
スラスラ書ける様になると思います。
30秒くらいを目安に書ければ十分かと思います。
また、書く時の大きさですが、
技能試験本番では、
問題用紙の余白に書く事に
なると思いますので、
A5サイズ以下に納まるくらいの
大きさで練習する事をお勧めします。
基本的な複線図を書く手順
- 電源・器具の記号を単線図と同じ場所に書く
- 電源からスイッチ以外の器具に接地線(白)をつなぐ
- コンセント・スイッチに非接地線(黑)をつなぐ
- スイッチから対応している負荷へつなぐ
- 電線接続箇所に印を入れる(リングスリーブ●、差込コネクタ■)
リングスリーブの場合圧着マーク(○・小・中)を書く - 接続箇所がジョイントボックスなら〇、アウトレットボックスなら□で囲む
- 電線に色を書く(接地線シ、非接地線ク)
- 色が書かれていない線に使われていない色を書く(赤はアなど)
2芯か3芯で判断してください。
基本、これだけです。
補足
- 1の器具を書く時に6のボックスも先に書く方もおられる様ですが、
先にボックスを書いてしまうと電線を書く際、接続箇所を無理矢理
〇なり□の中を通過させるように書かないといけないので
書きにくいです。 - 5~8は書きやすい順でいいと思いますし、慣れれば電線書きながら
色(シやク)、●を同時に書いていった方が早いです。 - 3色ボールペンを使用する場合、白線を青色で書けばシとか色の記入は、
当然省略できます。カチカチと色を変えながら電線を書いていく訳ですが、
こちらの方が速く、色の記入が省力できますので、
解りやすく見た目もスッキリします。
少しでも時間短縮をしたいなら3色ボールペンをお勧めします。
複線図の基本的な書き方
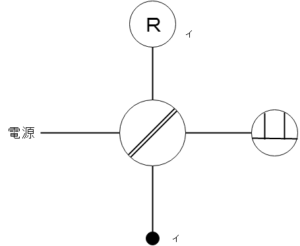
この単線図を複線図に書き直してみます。
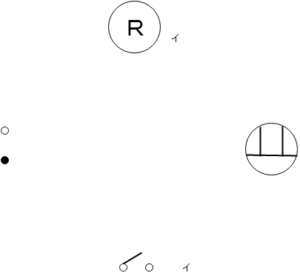
まず器具を単線図通りに配置します。
電源は非接地側を黒く
塗りつぶしておくと解り易いです。
スイッチも図の様に書きます。
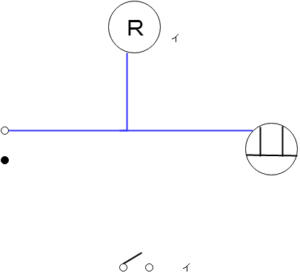
電源接地側とスイッチ以外の器具を
白線でつなぐ。
3色ボールペンで書くとして、
白線は青で書いています。
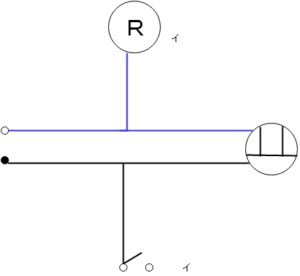
電源非接地側と
スイッチ、コンセントを
黒線でつなぐ
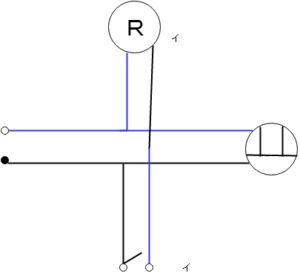
スイッチと対応している負荷をつなぐ
スイッチは黒が既に使われているので
接続箇所までは必然的に白。
接続箇所から負荷までは、
負荷には既に白がつながっているので
必然的に黒になります。
ここは色違いになりますが
問題ありません。
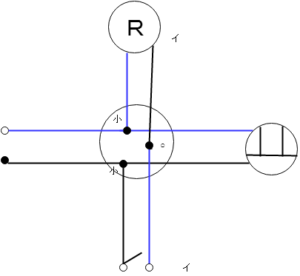
電線接続箇所に印を入れ、
(リングスリーブは●、差込コネクタは■)
リングスリーブの場合は、圧着マークも記入し、
接続箇所を囲み、
(ジョイントボックスなら○
アウトレットボックスなら□)完成。
慣れれば線を書きながら●なり■を
入れていけば速いです。
ボックスは最初に書く方もおられますので、
書き易い順で良いですし、
慣れれば書かなくても解ります。
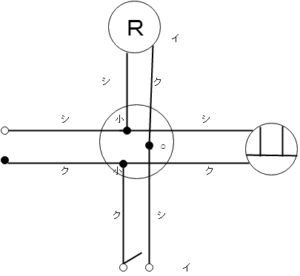
3色ボールペンですと⑤で終わりですが、
1色の場合、線の色は全て黒ですので、
各電線の横にクとかシとか電線の色を
書いていきます。
最後にまとめて書かなくても、
線を引きながらシ・クなど
確定箇所は同時に書いて行き、
最後に抜けている箇所を書けば
よいと思います。
以上、複線図の基本的な書き方でした。
これはあくまでも基本的な書き方で、
基本が解れば省略出来る所は
省略すれば良いと思います。
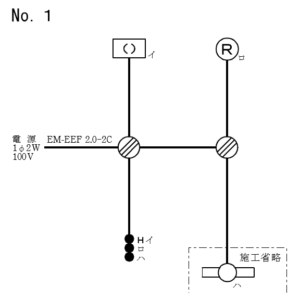

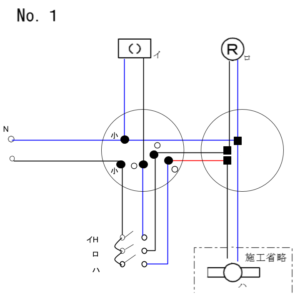


コメント